 |
 |
2001年1月〜 9月まで
南宮山 (岐阜県垂町)40m |
1月1日 5時出発 出発時曇っていたので初日の出は望めないと思っていたが、頂上に着く直前に雲が切れ、ご来光を仰ぐ ことが出来2001年の幕開けにふさわしいと感激 |
 |
| 金時山 (神奈川県 箱根町) 1212.5m 行程 大垣━金時神社車止━箱根仙石原登山口━矢倉沢峠━金時山━長尾山━乙女峠━乙女口━車止━大垣 |
1月14日 4時30分出発 昨夜より寒波襲来で天気予報は大雪情報 早朝雪がちらつくなか出発 しかし登り口につく頃から晴れ間が広がる。 登山道の両サイドは霜柱が白く光り、始めてみる光景 道はなだらかだったが雪が解け赤土に混じり滑ることしばしば アイゼンを車においてきたため山小屋で縄を買い靴に巻いて滑り止めにし下山した。それにしてもアイスバンに足をとられ装備の必要性を痛感。アイゼンの代わりに縄を巻いて滑り止めにした。昔からの知恵が今も生きていた。 乙女峠から撮った富士 |
 |
物見山 327m |
2月4日 天候に恵まれこの時期としては暖かい。ハイキングコースのやさしい山 万博開催が決まるまでは訪れる人も少なく、山百合が美しかったとのこと 今は途絶えていた。また昨年の台風で倒木が多く大正池が枯れていた。山里はまだまだ寒くあちこちに薄氷が張っていた。 |
 |
| 八鬼山 (熊野古道) 627m |
2月18日 登山道は思ったより整備されていた。この熊野古道は世界遺産の候補に挙がっているとのことで昔ながらの石畳と真新しい丸太で作られた参道とがミックスしていた。石像が所々に置かれ(30センチ程のもの)信仰を持つ人々が行き交うイメージであった |
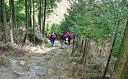 |
尾城山 (加茂郡白川村と恵那 郡加子母村との境) 789.2m |
4月8日 晴天 初夏を思わせる暖かさ 登り約1時間 下りゆっくりと休憩をとりながら下山で1時間 やさしいハイキングコースであった。「千代姫伝説のゆかりの山」ガイドブック紹介の二輪草 かたくりの花は見つからなかった。山腹にて明神山がみえたが、頂上は樹木が茂り展望は開けない。下山途中で猿の一団に会う。 |
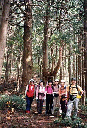 |
| 御殿山 (愛知県東栄町) 1133m |
4月15日 晴 車止めが800m近く 頂上まで大した道のりはなくハイキングコース 頂上近くにはまだ雪も残っていて寒かった。大垣では桜は満開だがこの付近はまだ蕾だった。頂上は樹木に覆われ展望は良くなかった。 此の時期になると一同 山野草を楽しみにするが今日は車止め付近でショウジョウバカマが見られただけだった。登り口付近でキジを見かける。 |
 |
小谷山(滋賀県湖北町) 495m |
5月4日 さわやかな五月晴れ 夜叉が池を計画するも倒木で車道が妨げられ計画変更 主人と二人で小谷山へ登る。全山が城の遺構 久しぶりに歴史散策をする。室町時代浅井亮政がこの地に拠を置き湖北を守った。はじめは尾根の主だったところだけだったが次第に勢力をのばし全山築城となった。歴史を振り返りながら心地よい風に吹かれ頂上では伊吹山を望み下山途中ではカモシカを見かけた |
 |
蓼科山 (長野県北佐久郡立科町と茅野との境)2538m1△ |
6月10日 (日) 曇 梅雨の中 晴天は望むべくも無いが、4時30分出発 一等三角点の蓼科山、晴れていればさぞや展望も良いであろうが先ずは降られる事も無くまずまずのお天気。7合目から鳥居をくぐって登山道に入った。カラマツ林の穏やかな斜面を馬返しまで登る。ガレた広い道を登り木の根が張った斜面を乗り越えると岩くずの溜まり場、天狗の露地に出た。ここからは通称ざんげ坂と呼ばれる急登が始まり私にとって第一番目の関門 将軍平の蓼科山荘に到着しホッと一息入れる。どっしりとした山頂が目前に迫り溶岩が堆積した急勾配の道を直線で登りテンポが落ちる。どっしりとした山頂が目前に迫り溶岩が堆積した急勾配の道を直線で登りテンポが落ちる。 山頂は広大な岩塊がひしめく溶岩台地。聞きしに勝る岩岩 中央の火口跡のくぼ地に高井明神が祀られていた。晴天であればさぞや眺望がいいだろうと話し合う。 一瞬の晴れ間に南東に八ヶ岳が見えシャッターチャンス!すぐにガスで見えなくなる。可憐な岩かがみの群生が見られた。所要時間 登り2時間 下り1時間半 |
  |
苗場山 (長野県下水内郡栄村と新潟県中魚沼郡津南町・南魚沼郡湯沢町との境) 2,145.3m |
7月29日・30日 雨も上がり猛暑の夏到来 今年は6月から高温の日が続き これから先が思いやられる。今月の予定は7月8日 夏焼城ヶ山 と7月29・30日の百名山の一つ苗場山 苗場山は奥深い山にもかかわらず人々に広く知られ信仰の対象になっ て来たが深 田久弥によれば この山が個性的で非凡だったからと述べている。特に広大な湿原には池とうが潜在し お花畑が広が っていると聞いて楽しみにしていた。 行程 29日 大垣→羽島IC→豊田・飯山IC→小赤沢ルート3合目車止→9合目(坪場)→苗場山 (泊)遊仙閣 30日 遊仙閣→山頂散策→9合目 (坪場)→車止→小赤沢温泉楽養館 入浴→大垣 |
|
| 3合目(車止)出発が10時15分 湿原で1時間ほど散策し山小屋 遊仙閣に着いたのが15時50分 山頂からの眺めはあまり良くない。空気がすんでいれば谷川岳 黒姫山 飯縄山が見える筈なのだが・・・僅かに鳥甲山の山頂を見ることが出来た。翌朝のご来光は厚い雲の間からほんの一瞬顔を覗かせた。帰りの下山の所要時間3時間半 素晴らしい湿原のお花畑が印象的な苗場山であった。帰途立ち寄った車止めの近くの温泉の湯は赤土色であった。噴出す時は透明だとの事 空気に触れて赤く変化するそうである。 |
天候晴れ時々曇り 早朝4時出発 登り口(小赤 沢ルート3合目車止1290M)に着いたのが10時15分 既に30台ほど駐車していた。雑木林 の中を登りはじめた。秋は紅葉の美しさが想像さ れるブナ ナラの樹林の中、森林浴が心地よい。 想像していたより登り坂が多く8合目あたりより周囲はささに覆われるが、管理され道は切り開かれていた。9合目まで一挙に急登 9合目からは俄に広々とした湿原が広がる。一同歓声をあげる。所々に地とうがあり、山野草の宝庫である。 特に群生して印象深かったワタスゲ トキソウ キンコウカ ミヤマホタルイをデジカメに収めた。 地とうのなかのミヤマホタルイはこの苗場山命名の由来となったとの説明書きがあり一同納得   |
|
湿原に咲いていた代表的な花4種 ワタスゲ トキソウ キンコウカ ミヤマホタルイ
| 例年この時期はあまり身体の無理がきかなくなり、比較的楽な登山プランへの参加となる。ウーン残念! 他のメンバーの計画 2泊3日で燕岳(2762.9m) 大天井岳(2922m) 常念岳(2857m)蝶ヶ岳(2664.3m) しかし悪天候のため取りやめとなり谷川岳に変更した。これも私は不参加 |
今月の参加は5日の寺田小屋 それと23日メンバー夫妻の西国33ヶ所札所巡りに同行 滋賀県の竹生島の宝厳寺 観音正寺に詣でる。
竹生島 琵琶湖きっての景勝地で”竹生島の沈影”琵琶湖八景一つにあげられている。 |
8月23日 メンバー夫妻の西国33ヶ所札所巡りに同行 滋賀県の竹生島の宝厳寺 観音正寺に詣でる。 |
 |
寺田小屋山 (岐阜県益田郡下呂町と 小坂町 との境) 1505.1m |
行程 大垣→県道終点車止→登山口標識→稜線→寺田小屋山→車止→大垣 |
8月5日 6時30分出発 天候晴れ時々曇 白草山登山(昨年登る)の林道の分岐 道はがたがたの悪路 終点は登り口ではなく林道をさらに歩くこと30分 標識が登山口の反対側にあり、見過ごしてしまうところだった。ここでの高度1200M 頂上までの標高差300M 楽に登れそうだと思ったが、頂上に近づくと周囲は藪で覆われ道は狭く、むき出しの顔や腕をかばう。頂上近くには以前使用していた無線中継所の建築物の残骸があった。がもう役目を終えて粉々に・・・ 山頂の景色はあまり良くない。楽しみにしていたお目当ての御嶽山は雲がかかり眺望は良くない。あまり強い印象が残らない山であった。車止めからの所要時間1時間50分 下山1時間30分 下山後乗政温泉で汗を流す。 |
 群生していたウスユキそう  雲がかかった御岳 |
夜叉ヶ池 (岐阜県坂内村) 1100m |
今まで2度 登山計画が土砂崩れなどの影響で実現できなかったが、3度目のトライで、夜叉ヶ池登山実行 メンバー4人の登山 台風の影響で雨の予想を覆し晴天 又気温も真夏の暑さ ハイキングコースと思い込んでいたが急登もあり所々足場も悪かった。西濃では有名な「夜叉姫竜神」伝説の謂れとなったのがこの夜叉ヶ池 古くから西濃地方に残る夜叉姫の秘話は長く伝えられ、江戸時代大垣藩は揖斐川の水源として手厚く保護 雨乞いの祭り事は重要な行事であった。出発から40分幽玄の滝を越えると夜叉壁と呼ばれる大岩壁が前方に迫る。 しばし足場の悪さに気をとられたがいよいよ池の又谷の最源流である。途中 山野草が目を楽しませてくれる。岩の間 草の間 所々から湧き水が流れ足を踏ん張って登る。ヤナギなどの低木林と草地に囲まれて紺碧の池が横たわる。東側はブナの林 池の対岸、福井県側に小さな裸地があり竜神を静めるものだという祠が祭られていた。 所要時間 林道終点より1時間40分 下山1時間20分 |
湖水の美しさ拡大してみてね   |
![]() 10月は予てから計画していた東北地方の山行と観光の5泊6日の旅行を次ページへ
10月は予てから計画していた東北地方の山行と観光の5泊6日の旅行を次ページへ